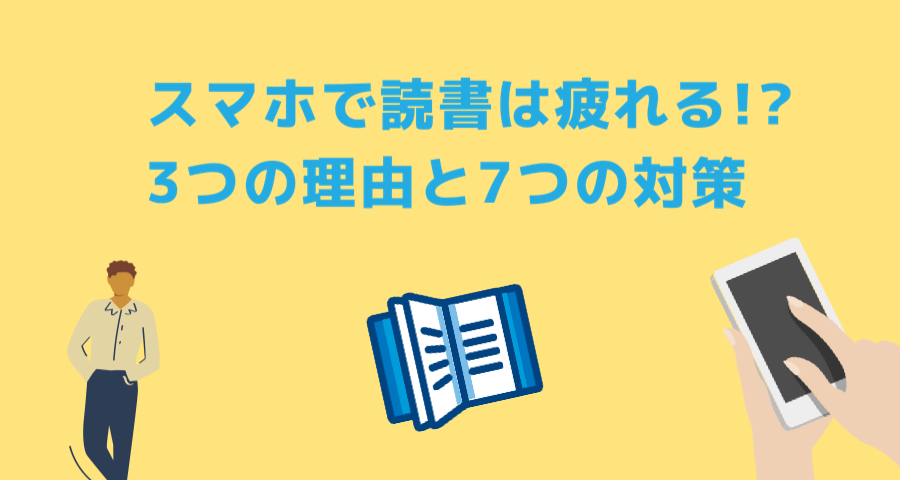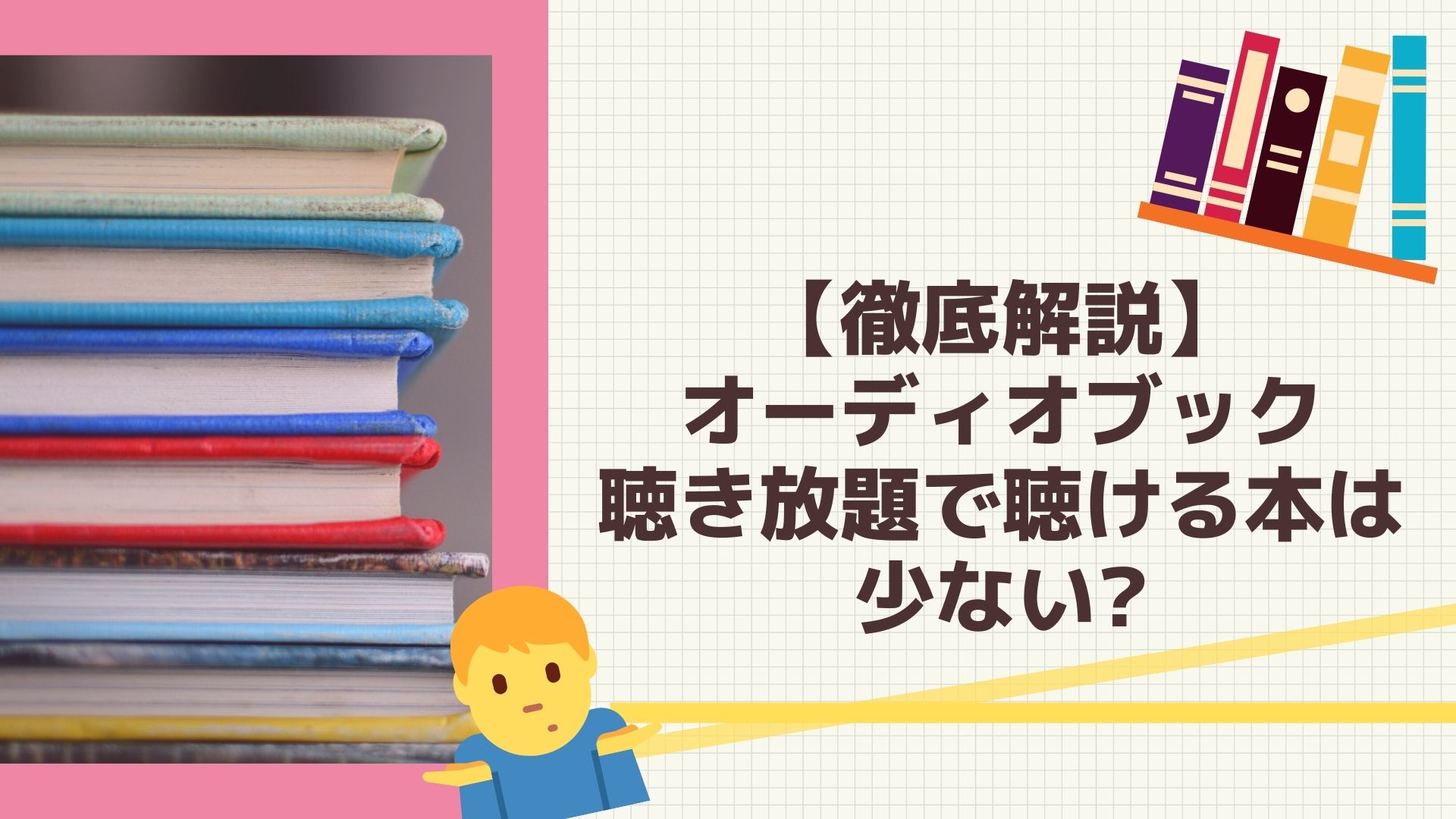今や読書は本だけではなくスマホやタブレットで読むのが当たり前の時代です。
スマホは1台でたくさんの本を持ち運ぶことができるため、どこでも手軽に読書ができます。
一方で、

という方もいるのではないでしょうか?
スマホで読書は効率が良いので、疲れることを理由に本にこだわるのはもったいないです。
この記事ではそんな人のために、スマホで読書が疲れる3つの理由と疲れないための5つの対策について詳しく解説していきます。
スマホで読書が疲れる理由

疲れる理由①:スマホの小さい画面で読書すると疲れる
スマホはポケットにも入るサイズが大変便利ですが、その分画面も小さくて表示できる文字サイズも小さいです。
2本の指でスマホの画面をつまむ操作(ピンチ)で文字を大きくすることはできます。
しかし、PCやタブレット端末と比べると限界があるため読みづらいと感じることは多いです。
小さい文字を読むことは単純に疲れますし、小さい文字を読むために目と画面の距離が近くなることも疲れの原因の一つです。
画面と目が近くなると、多くの光が目に入ることで目が疲れます。
このように画面のサイズが小さいというのはスマホ読書で疲れる原因になります。
疲れる理由②:スマホ画面から出るブルーライトで目が疲れやすい
スマホのLEDディスプレイにはブルーライトが多く含まれています。
ブルーライトは波長が短いため散乱しやすい性質をしています。
この性質がまぶしさやチラつきを起こすため、脳はピント合わせに苦労します。
また、ブルーライトは人の目で見ることができる光の中でも強いエネルギーを持つ光です。
そのため、目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達してしまいます。
ブルーライトを浴びると光の量を減らすために瞳孔を縮めようとして目の筋肉が酷使されます。
これが眼精疲労やドライアイ・肩こりや頭痛の原因になります。
理由③:読み飛ばしが難しいため疲れる
本は、ページ全体を見ながら必要なところだけを読む「読み飛ばし」ができます。
しかし、スマホでの読書は、画面に表示できる範囲が限られるため読み飛ばしが難しいです。
結果的に一冊を読み終えるのに時間が掛かりスマホを長時間見続けることになります。
長時間スマホを見続けることで目を酷使し、疲れ目の原因になります。
また、興味がない箇所の読み飛ばしが難しいため、思うように読み進めることができないことにストレスを感じる人もいるでしょう。
こういったストレスからもスマホでの読書は疲れを感じやすくなります。
スマホで読書すると疲れる場合の5つの対策
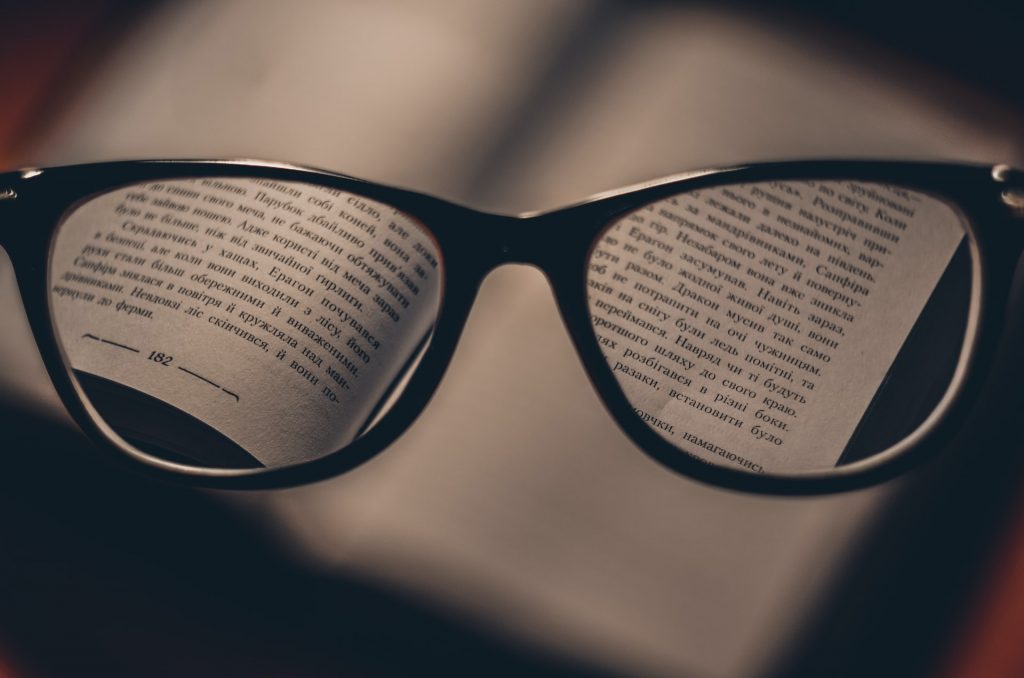
ここからは先ほどのスマホ読書で疲れる理由を踏まえて対策方法を5つ紹介していきます。
スマホで読書をすると疲れてしまうという人はぜひ実践してみてください。
対策①:ブルーライトカット眼鏡を使用する
ブルーライトカット眼鏡を使用すれば、目が疲れる原因となるブルーライトをカットすることができます。
現在では、ほとんどの眼鏡の専門店が取り扱っていて、大手の通販サイトでも購入できます。
「度付き眼鏡にブルーライトカットを入れることができるタイプ」や「度無しのブルーライトカットを目的としたタイプ」など種類も豊富です。
デザインが優れたおしゃれなブルーライト眼鏡もあり、1つは持っておくとパソコン使用時にも活用できます。
ブルーライト眼鏡のレンズの中には、着色されているタイプがあります。
着色レンズは抵抗があるという方もいるかと思いますが、無着色レンズと比較すると着色タイプの方がブルーライトのカット率が高いです。
カット率が高ければ、目への負担も軽減されるため、購入時にはブルーライトのカット率も忘れずに確認しましょう。
対策②:オーディオブックで耳で読書をする
本の内容を音声で提供しているオーディオブックというサービスがあります。
このオーディオブックを使えば目を使わずに耳で読書をすることができるため、目の疲れを防止することができます。
手を使わずに、耳から本の内容が入ってくるため「ながら読書」ができて時間を有効活用することもできます。
「ジョギング」「皿洗い」「掃除」をしながら音楽の代わりにオーディオブックで読書ができます。
また、防水タイプのスマホや防水ケースを使用すれば、入浴中に目をリラックスさせながら読書を楽しむこともできます。
オーディオブックについては【読書】Amazonオーディオブックとは?料金・使い方を徹底解説で詳しく解説しています。
対策③:専用保護フィルムでブルーライトをカット
ブルーライトカット効果がある専用保護フィルムをスマホに貼るのもおすすめです。
ブルーライトカット眼鏡と比べて安価なのでお求めやすいです。
スマホの画面に直接貼ることが出来るので、常にブルーライトカット効果が得られます。
眼鏡のように持ち歩く必要はないですが、ガラスフィルムは割れる可能性があるので注意が必要です。
また、眼鏡と同様に製品によってブルーライトのカット率が異なるので、購入時は確認をしましょう。
対策④:Kindle PaperWhiteを使って本を読む
Kindle PaperWhiteは、Amazon.comが発売した電子書籍リーダー専用の端末です。
Kindle PaperWhiteの画面は、マルチタッチ対応の電子ペーパーを採用しています。
電子ペーパーは紙と同様に光が当たることで目で見ることができます。
液晶画面のようにバックからのライトを必要としないので、ブルーライトはほとんどゼロに近いです。
加えて、直接目を照らさないフロントライト方式のため、液晶画面と比べると目が疲れにくいです。
また、文字サイズや明るさ調整機能があり、質感も紙に近いため目に優しい読書が出来ます。
対策⑤:ブルーライト目薬を活用
目薬にもブルーライトによるダメージをケアする商品があります。
ピント調整で凝り固まった筋肉をほぐす成分や目の細胞の修復を促進する成分などが配合されています。
これらの成分が目の疲れを改善してくれます。
ドライアイやかすみ目などにも有効な商品も豊富にあり、症状に応じて選ぶことができます。
一方で、種類が豊富なのでどれを選べば良いのか分からないという方もいらっしゃると思います。
そんな方は、ドラッグストアの薬剤師に相談するか眼科を受診して症状に合った目薬を処方してもらうことをおすすめします。
疲れを感じた時にいつでもリフレッシュできるように常備しておくと良いでしょう。
対策⑥:目に良い成分を含むサプリメントを摂る
ブルーライカットなどで目の酷使を減らすことに加えて目に良い成分を補うことも大切です。
目に良い成分には、ルテインやアントシアニン、ビタミンなどがありますが、いずれもサプリで補うのがお手軽でおすすめです。
ルテインは、ブルーライトと紫外線を吸収する働きがあり、網膜細胞を守ってくれることが期待されています。
アントシアニンは、抗酸化成分ポリフェノールの一種です。
私たちの目には、ロドプシンという見たものを情報として脳に伝達する物質があります。
目の酷使などによりロドプシンが減少すると、目の疲れによる症状が出てきます。
このロドプシンの再合成を促すのがアントシアニンなのです。
市販のサプリメントは、ルテインとアントシアニンの両方が含まれているものやビタミンが加わったものなど様々です。
成分の働きを理解して、疲れ目に必要な成分を補いましょう。
対策⑦:ホットタオルやマッサージで目を癒す
スマホの読書による疲れ目や疲れ目による、頭痛・肩こりには、目を温めるのが効果的です。
目や目の周辺を温めることで血行や新陳代謝が良くなるので疲れ目による頭痛や肩こりにも効果的です。
また、まぶたの中の脂腺から脂分が分泌されやすくなり、脂分が眼球の表面に膜を作ることでドライアイの改善にもなります。
目を温める方法としては、湿らせたタオルを1分程、電子レンジで温める蒸しタオルが簡単です。
この蒸しタオルで5分くらい目や目の周辺を温めるととても心地よいです。
目を温めるアイマスクも市販されています。
使い捨てタイプや繰り返し使えるタイプがあり、どちらも簡単に目を温めることができます。

商品詳細→『あずきのチカラ 目もと用』
最近では、遠赤外線で目を温める機能がついたアイマッサージャーなどもあります。
こちらは、スチームやマッサージ機能付きもあるので血行を促しながら筋肉の凝りも解せます。
疲れを溜めないように日々、ケアをすることも大切です。
スマホ読書で快適に読書時間を確保しよう!
スマホでの読書が疲れるのは、ブルーライトや小さな画面で目を酷使することが大きな要因の場合が多いです。
ブルーライトメガネを活用したり、目薬やアイマスクでケアをすることで目の疲れを防止につながります。
スマホでの読書は場所を選ばず、少し時間ができた時にサッと取り出してすぐに読み始めることができます。
スマホで読書をすると疲れる理由と対策を理解して、上手にスマホ読書と付き合って知識の幅を広げていきましょう!